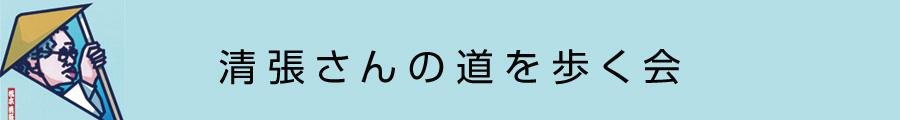

≪第5回「足立山麓の松本清張さんをしのぶ会」≫
💎💎 特別掲載 💎💎
今、「清張さんの歩いた3本の道」というパンフレットの「英語の道」を読みながら、父幸一郎が、<こんなことをしていたのか>という思いを強くしている。父は私が5歳の時
に病没したので、私の頭の中には父との思い出が点在しているに過ぎない。しかも、その思い出といっても数多くあるわけではなく、指折り数えて見ても片手の指で事足りるくらいの少なさである。そして、当然のことながら、その数少ない記憶の中には父が作家になる前の清張さんに英会話を教えていたというものはない。当然と言い切ったのは、父が清張さんに限らず他の人に英会話を教えていたとしても、それは5歳に満たない子どもにとって記憶に留めるほどの衝撃的な出来事でもないからである。また、父にとっても、清張さんは朝日新聞西部本社の後輩の一人であって、それ以上でもそれ以下でもない関係だっただろうと思うが、父がアメリカで培ったボランティア精神を発揮して清張さんを受け入れたと言うだけのことで、何ら気負う必要もない日常的な小さな出来事だったに違いないのだ。
ところが、清張さんは、軽い気持ちで始めた父とは裏腹に、最初から全力で父の胸に絡み付いて、熱心に父の許に通い続ける一方で、その清張さんの真摯な姿勢に心打たれた父は、途中から単に清張さんの英会話の相手になるのではなく、清張さんに正しい英語を教えようという考えに変わっていったように思われる。何故、そう思うのかと言えば、それは、今、この「思い出」を書きながら、私が高校の2年のころ、母弥寿子から聞いた「父が清張さんの為に『英会話練習帳』を手作りした」という話を思い出したからである。母からこの話を聞いた時は、何も感じなかったが、今思えば、父が清張さんの為に「英会話練習帳」を手作りした行為そのものが、父が指導方針を変更して、本気になった証しとなるだろう。(この「テキスト」は、残念ながら、我が家にも清張さんの資料の中にもありません。)また、「テキスト」の作成過程を考えると、朝日新聞の通訳室にはタイプライターがあったはずなのに、それを使わずに手書きで作ったということも、父が清張さんの熱意に自分も熱意で応えたのだと思う。また、些細なことだが、個人的なことで会社の備品を使わなかった父の律儀さを垣間見たようで誇らしく思うのだが、このような感傷はさておくとして、父はこの「英会話練習帳」を土台にして清張さんの英語を本物にしてやる為のプランを練っていたのではなかろうかと思えるのだ。しかし、このプランは、父が58歳という若さでこの世を去ったことで、実行されることなく、父と清張さんの英語劇も開幕から僅か半年で幕が引かれてしまい、父も清張さんも目標を達成できずに終わったことを残念に思ったことだろう……。
「無念」の二文字を頭に思い浮かべながら、今度は、「清張さんの散歩道」に目を移すと、清張さんは、「昼休みに会社を抜け出して広寿山福聚寺へ散歩に出かけた」とある。遊外の俳号を持ち、俳句を嗜んでいた父もまた広寿山福聚寺の界隈を散歩するのが好きだった。時々、私も父に連れられて散歩をした記憶がある。この記憶は頭の片隅にある木綿針で突いた穴(点)くらいの小さなものだが、目を閉じれば、福聚寺の鬱蒼とした森の中を散歩する三人の姿が浮かび上がってくる。私が父と紳士(大人の男性)に挟まれて歩いている姿である。だが、この紳士が誰なのか全く記憶がない。否、記憶がないのではなくて、当時の私にはどこかの<おじさん>くらいの認識でしかなかったに違いない。しかし、今、こうして父や清張さんのことを回想していると、この紳士は清張さんだったのではないかという思いがひしひしと押し迫ってくる……と、同時に、今年の3月6日に心筋梗塞で他界した兄襄司が清張さんの思い出話をする時、「清張さんのように勉強しなさい」と母に叱咤激励されたと口癖のように言っていたが、兄に何度も母の言葉を繰り返し言わせたように、清張さんの学ぶ姿勢、あらゆる機会と時間を利用しながら寸暇を惜しんで勉学に励む清張さんの執念と気迫を考え合わせると通勤時だけでなく父の散歩にも同行して英会話を学んだ可能性を否定できず、私の想像も的外れではないだろうと思えるのだが、今に至っては確認する術もなく残念である。
少し話が戻るが、私が「テキスト」の話を母から聞いたのは高校2年のころだったというのは、上述した通りだが、この年は父の13回忌の年でもありました。昭和33年のことです。昭和33年と言えば、清張さんが意欲的な作品を次々と世に送り出して大作家への道を登っていたころですが、突然、我が家に東京から小包が届きました。送り主は松本清張さんでした。小包を開けると真新しい三冊の本が出てきました。清張さんの代表作の「点と線」、「眼の壁」と「ゼロの焦点」の三冊です。各々の本の扉の中央に「奉献 竹野幸一郎先生」とあり、左下横に「松本清張」の署名がありました。清張さんが、父の13回忌に合わせて、自作品を献本して下さったのです。一冊の本の中には数枚の百円札も挟まれていました。(「テキスト」の話は、この時、膝の上に置いた清張さんの本の表紙を掌で摩りながら、母が問わず語りに語ったものです。)清張さんの三冊の献本とお金は、父の仏前に長い間供えられていましたが、私には噂話でしかなかった「父と清張さんの関係」が事実だったことを教えてくれただけでした。しかし、姉美代子は違っていたようです。姉は長年自分の心に深く刻まれた思いを「松本のおじさん」というエッセイに託して発表したのです。そして、姉のエッセイが、貴会及び関係者の目に留まり、「清張さんの歩いた三本の道」の「英語の道」に繋がる切掛けになったと聞くに及んで姉共々光栄に思っております。父と清張さんの短くて小さな関係を丁寧に掘り起こして下さった貴会及び関係者の皆様のご尽力に対し心よりお礼を申し上げます。また、この度は、私にまで「父と清張さん」のことを書く機会を頂いて、久し振りに父を回想しながら、父と清張さんは英語を教える人と教わる人の関係ではあるが、お互いに打算のない、教える側の誠意と教わる側の熱意がぶつかり合い、清張さんの熱意は父に伝わり、父の誠意も清張さんへ伝わって、二人の関係が短期間であったにもかかわらず、二人の心が強い絆で結ばれていたのだ…と思うのですが、如何だろうか?
尚、献本の三冊のうち、「点と線」と「ゼロの焦点」は現存しているが、「眼の壁」は行方不明となっている。また、母は献本のお礼に湖月堂の栗饅頭を清張さんに届けたそうです。
巣山健太はJRの品川駅を降りて八月初旬の太陽に照らされながら、高台のホテルへ向かって歩いていた。
「ねぇ、白髪さん、もう少しゆっくり歩いてよ!」
健太は、突然、背後から女性に声をかけられ、驚いて足を止めた。たが、自分の白髪を弄る女性は一人しかいなかったので、誰が声をかけてきたのか、直ぐに察しがついた。振り向くと小柄な女性が小走りに近づいてきた。やはり菅井由紀だった。彼女とは小中高と同じ学校に通ったが、特に小学校はずっと同じクラスで級長と副級長を長くやった仲だった。
「おい、会うたびに、どうして、白髪さんと呼ぶんだよ」
「あら、そう。だって、白髪だもん。それにさあ……」
「何だよ? 」
「とても目立つのよ。さっきも、あっ、白髪さんだって、直ぐに分かったしね」
「おい、こんどは目印か……今日、家に帰ったら真っ黒に染めちゃおう」
「ダメ、ダメ。目印というのは、今、思いついただけなの。本当は、ほら、わたしの髪の毛を見てよ。どう、この中途半端な胡麻塩頭、この前会った時と全然変わってないでしょ。貧相というか、みすぼらしくて、わたし、大嫌いなの。毎日、早く白くなれって願っているのだけれど、もう何年も変わらないのよ。あのねえ、健太の白い髪はわたしの憧れなの。そして、健太のような白い髪になるのが、わたしの夢なのだから絶対に染めちゃ駄目よ」
健太は軽く笑みを浮かべて肯いた。そして、突然、由紀の手を握って肩を並べて歩いた。健太も由紀も口を閉じたまま、握る手の強弱で語り合いを続けながら、「K・N高校東京支部同窓会場」と書いた紙を振り翳して道端に立っていた幹事の道案内に従って数メートル先の角を曲がった。すると、その角からホテルへ向かう道はスキーのジャンプ台を下から眺めたような形状をしていた。緩やかな下り坂を歩くのは楽であったが、急勾配の上り坂になると太陽の熱も加わって踏み出す一歩一歩が緩慢になった。途中で一休みしたくなるような暑さと急勾配の坂道であったが、どちらからも休もうとは言わずに手を強く握り合い支えあいながら、重くなった足を踏みしめて坂道を登って行った。
同窓会の後、JRの品川駅で別れ、健太は横浜へ、由紀は吉祥寺へと帰って行った。
夏が過ぎ、厳しい残暑が続いたが、夜になると、虫の声が聞こえ、肌にも秋冷を感じる十月中旬になって、由紀が、別れ際に「後でメールするね」と言ったのを思い出した。由紀とは五年前の同窓会で再会して以来、何かあれば、メールだけで連絡を取り合っていたが、最近、由紀のメールを見た記憶がなかった。それでも、見落としていることもあるので、念のため、過去のメール記録をチェックした。しかし由紀からのメールはなかった。健太は、「後でメールするね」と言いながら、由紀から音沙汰がないのが気になって由紀にメールした。
「由紀さま、秋の夜、虫の声を聞きながら、『後でメールするね』と言ったあなたの言葉を思い出しました。あれは、何だったのでしょうか? 」
由紀からすぐ返事が来た。
「健太さま、ごめんなさい。連絡が遅くなりました。同窓会の後、独身の身軽さで友だちに誘われるまま、根津や上野の美術館に行ったり、韓国にも行ったりして、あちこちと出歩いていたので、メールをするのを怠りました。実は、わたしの後輩の女性が小倉で演劇活動を続けていて、彼女の劇団の特別公演に招待されたので、文化の日に小倉に行くのですが、健太さんも一緒にどうかと思いお誘いのメールをするつもりでした。幸いなことに健太さんからメールがあったので、この場を借りて、突然ですが、わたしと小倉へ行ってみませんか? 」
健太の返事。
「由紀さま、三日は予定あり、観劇は無理です。でも、四日からなら可能ですので、由紀さんの滞在が長くなっても構わなければ、久し振りに行って見たいところもあるので、行こうと思いますが、どうですか? 」
由紀の返事。
「健太さま、わたしの滞在が長くなっても構いません。また、健太さんの行って見たいところへも喜んでお供します。わたしは公演日の前日に小倉へ行きますので、十一月四日にお会いしましょう。わたしは小倉駅のホテルを予約しています。」
健太の返事。
「由紀さま、了解。一泊二日では物足りないので、二泊三日にしました。また、由紀さんと同じホテルの予約も取れました。飛行機は早朝の便にしましたので、午前中にはホテルへ着きます。それでは、当日、ホテルのロビーでお会いしましょう。」
一週間後、健太は北九州空港に降り立ち、数十年ぶりの故郷の空気を思い切り胸に吸い込んだ。空港からバスで小倉駅まで行き、ホテルに向かった。ホテルに入ると由紀が駆け寄ってきた。
「おはよう」「やあ」
と挨拶を交わしたが、由紀は何時もの雰囲気とまるっきり違っていた。
「おい、その頭……」
「驚いた? 韓国のヘアサロンで染めて貰ったのよ」
「へえ、変われば変わるもんだなあ」
「どう、素敵でしょ」
「悪くはないね」
「ありがとう。これで、似た者同士になったわね」
「まあな……」
「それはともかく、早くチェックインをしたら……」
と由紀が頬をピンク色に染めて言った。健太はチェックインを申し出たが、まだ部屋が準備できていないと言うので荷物をフロントに預けて、由紀と手を取り合って小倉駅の近くの商店街から散策を始めた。二つの商店街と旦過市場を通り抜けるとモノレールの駅があった。そこからモノレールに乗った。モノレールは、かつて、路面電車が走っていた通りの上を走り、その軌道の下は自動車道になっていた。次の駅でモノレールを降りて、黄金市場の「うどん屋」に立ち寄った。丸天か素うどんか、迷った末に素うどんを注文した。「これだ。この味だ」と心の中で呟きなから夢中で食べ終えた。
「満足した? 」
と由紀が笑った。
「ああ、美味かった。麺も汁もこうでなきゃ、うどんじゃないよ」
「健太は、何時、東京のうどんに慣れたの? 」
「未だに慣れないね。あの汁の色に違和感を覚えて以来、東京ではうどんは食べなかったのだが、最近は東京でも讃岐うどんの店が増えただろう。だから、うどんで悩むこともなくなったけど……」
「そうねえ、東京の汁は蕎麦ならいいけど、うどんの汁は西の方が勝ちだわね」
と由紀が同意した。健太と由紀は「うどん屋」を出てから、A中学校へと向かった。A中学校を鉄柵に沿って半周して、競輪場や野球場の場所を確認しながら、S小学校へと足を運んだ。S小学校では、鉄柵に張り付いて、暫くの間、運動場で遊んでいる子供たちを眺めていた。母校はどちらも昔と同じ場所にあったが、木造の校舎は鉄筋校舎になっていた。健太と由紀は同時に鉄柵を離れ、足立山に向かって、通学路を逆に辿り、町名を頼りに、由紀の家の跡地(大畠)を訪ねた。しかし、そこには大きな道路が幾つも出来ており、由紀の家がどのあたりだったのか、見当もつかないほど、激しく変貌していた。健太はその場所から緩やかな坂道とその先の家並を目で辿り、山襞に隠れたM神社の辺りに視線を移した。M神社から視線を緩やかに下げて、自分が生まれ育った家の辺りの家並(妙見)を暫く眺めた後、足立山から吹き降りてきた風に身震いをしながら、由紀の手を引っぱって足早に市内へ戻って行った。 市内に戻ると既に太陽は西に沈み、小倉の街はネオンの七色に囲まれていた。まだ、夕食には少し早い時間だったので、海の見える場所まで歩いて行った。
「あの黒い大きな船、どこへ行くのかしら? 」
と由紀が言った。
「どこへ行くのか、どこへ帰るのか、分からないけど、昔なら南極の海へと言うロマンを語れたのだが、捕鯨が禁止になって、捕鯨船の母港、あの二つの港はどうなったのかなあ」
「太洋漁業の下関と日水の戸畑ね。八幡製鉄も西鉄の電車もなくなっているし……」
「今日、歩いたところでも、大池、水田、農水溝、夫婦池、無花果畑、炭坑の痕跡すらなかったし、炭坑以外は、子供の頃の遊び場だったんだが、どこを歩いても土や水や空気の臭いが全く違っていたから、異郷にいるみたいで、何だか複雑な気持ちだったなあ」
「あの足立山が目の前になかったら、今、故郷の小倉にいると思えないわねえ」
「ああ、国際都市に大変貌した故郷の姿を目の前にしたら、昔の幼い日々が懐かしくなって、少し感傷的になっちゃったなあ」
「昭和や平成という時代の流れと共に故郷も変わって、わたしたちも、こんな白髪頭になったんだから……感傷的になっても仕方ないわよ」
「それに俺たちは東京の暮らしの方が長くなったからなあ」
「寒いわ。ねえ、健太、もうホテルに戻ろうよ」
海峡を渡ってきた風が全身に絡み付いてきた。由紀が健太の腕を取り胸の膨らみを押し当てた。健太は上着の襟を立てて風を避けながらホテルに戻れば何が待っているのか、そして、それを超えれば、二人の新しい生活が始まるだろうと考えた。しかし、それは極めて複雑であり、やっかいなことの始まりであることも、はっきりと分かっていたのだった。
●昭和16年、小倉市妙見町(現・小倉北区妙見町)に生まれる。
●早稲田大学・第一文学部・文学科露文学専修卒業。
●日商岩井(現双日)勤務時代に駐在したブルガリアでの生活経験から下記❶~❸の著書を発表。
●竹野 憲司さん(筆名:越田 邦彦)の文学的実績
1.第12回(2018年度)北九州文学協会文学賞・小説部門
「隔離病棟にて」で <大賞>を受賞
2.出版
❶ブルガリアの笑いの発信地「ガブロヴォ・アネクドートの旅」(新風舎)
❷ブルガリアの笑い、ガブロヴォ・ジョーク(彩図社)
❸中央アジア紀行「20世紀のカザフスタン」(彩図社)
以上